

叡啓大学で開催された国際シンポジウムの成功を振り返る
叡啓大学での国際シンポジウム「ブルークレジットの現状と将来」
2024年12月10日、広島市にある叡啓大学にて、公益社団法人化学工学会 環境部会水環境分科会が主催する国際シンポジウム「ブルークレジットの現状と将来」が開催されました。本シンポジウムでは、大学が後援を行い、参加者68名が集まる成功のイベントとなりました。今回のシンポジウムでは、叡啓大学の下ヶ橋雅樹教授がオーガナイザーを務め、5名の学生が通訳として参加。通訳を担当した学生たちは、これまでも多くの経験を積んできた優秀なメンバーです。
特に、4年生の吉本考希さんは、学生生活や短期留学を通じて培った英語力を生かし、今回初めて英語から日本語への通訳に挑戦しました。
講演者と内容
シンポジウムでは、多彩な講演者が集まり、それぞれの視点から「ブルークレジット」に関する情報を共有しました。ユネスコ政府間海洋学委員会(IOC)議長の道田豊氏や、フィリピン大学のLindsay Young教授など、学界・産業界からの講演者が登壇し、具体的な取り組みや研究成果を発表しました。
以下は、主要な講演者とそのテーマです:
- - 道田 豊 氏(叡啓大学参与、東京大学 総長特使)
- - Dr. Lindsay Young(フィリピン大学教授)
- - 弓掛 丈 氏(株式会社ひろぎんホールディングス)
- - 小杉 知佳 氏(日本製鉄株式会社)
- - 酒井 裕司 氏(工学院大学准教授)
このシンポジウムは、各講演者の専門技術や取り組みを通じて、「ブルークレジット」というコンセプトの重要性を参加者に理解してもらう貴重な機会となりました。
学生の通訳体験と今後の展望
吉本考希さんは、逐次通訳を通じて多くの学びがあったと語ります。「私にとって初めての英語から日本語への通訳は、大変な挑戦でしたが、専門的な内容を正確に伝えるために事前準備を行いました。この経験は、今後のキャリアに大きな影響を与えると感じています」とのこと。彼はアカデミックなシンポジウムでの通訳業務を通じて、様々な専門の内容に対応する能力の重要性を痛感しました。
感謝の言葉と成功の成果
下ヶ橋教授は、シンポジウム終了後に「参加者の皆様が年末の忙しい時期にもかかわらず足を運んでくださり、心から感謝しています。また、学生たちの情熱がなければ成功は難しかったでしょう」と述べ、学生たちの努力を称賛しました。
シンポジウムは参加者同士の交流も活発に行われ、さまざまな意見が交わされることにより、より良い人と海の関係を築く第一歩となったに違いありません。
叡啓大学にとって、今回のシンポジウムは単なるイベントにとどまらず、未来へつながる気づきを多くの人々に与える意義ある場となりました。今後もこのような国際的な交流を通じて、人々の意識が高まることを期待しております。
ここから叡啓大学の公式ウェブサイトで、さらに詳しい情報や関連資料を探すことができます。
叡啓大学ウェブサイト
これからの環境問題解決に向けた継続的な取り組みに対する期待が高まる中、叡啓大学の役割はますます重要になるでしょう。



トピックス(イベント)





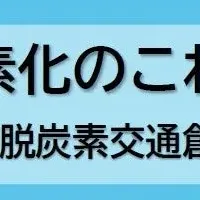

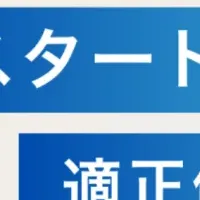
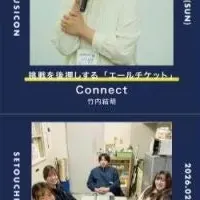
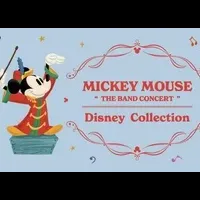
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。