

叡啓大学で行われたプロジェクトフレームワーク体験ワークショップの詳細
叡啓大学でのプロジェクトフレームワーク体験ワークショップ
2025年6月27日、広島市中区にある叡啓大学のプロジェクトワークスペース(PWS)で、特別な体験ワークショップが開催されました。イベント名は「叡啓プロジェクトフレームワーク体験ワークショップ」。このワークショップは、企業や自治体の関係者が叡啓大学で実施している課題解決演習(PBL)で活用されている「プロジェクトの進め方の型」(Project Framework)を実際に体験し、その理解を深めることを目的としています。
ワークショップの内容
当日、参加者は学外から招かれた8名で、学生と同様のプロセスを通じて実践に挑みました。具体的には、「問いを立て、構造化し、関係者にインタビューを行う」という流れです。これは、現実の課題に直面した際に、どのように思考を整理し、関係者と対話するかを学ぶ貴重な時間となりました。
叡啓プロジェクトフレームワークとは?
叡啓大学独自の「叡啓プロジェクトフレームワーク」は、実社会の問題解決に向けて学生たちが有効に活用できるように設計されています。このフレームワークは、プロジェクトの初期段階で「なぜその問題に取り組む必要があるのか」「誰のために、何を、どう実現したいのか」を整理する思考過程を支えます。これにより、価値創出へとつながる道筋を形成するための対話と考察の枠組みが提供されます。
ワークショップの進行
ワークショップは、ファシリテーター定金教授が叡啓大学の課題解決演習やプロジェクトフレームワークの全体像について説明するところから始まりました。その後、参加者は4名ずつのグループに分かれ、プロジェクトフレームワークの前半部分を実際に体験しました。
具体的なステップは以下の通りです:
1. 「誰のどんな困りごとに向き合うのか」を定める
2. 困りごとの構造や背景要因を整理する
3. 何を明らかにするために、どのような聞き取りを行うべきかインタビューを設計する
参加者同士が対話を重ねることで、それぞれの視点が交わり、問題の構造化が進んでいく過程が「学び」につながることを実感していました。
参加者の声
参加者からは様々な感想が寄せられました。以下のような声が印象的です:
- - 「ワークを通じて学んだインタビューの手法は、普段の仕事にも役立てられそうです。」
- - 「短時間で思考を回転させるのが難しかったですが、非常に重要だと実感できました。」
- - 「学生の段階でこのやり方を学べる叡啓生が羨ましい。」
- - 「感覚的に行っていたことを言語化できたのが良かった。」
- - 「問いに戻って考えることの大切さを再認識できた。」
実際に手や頭を使い、対話しながら体験することで、プロジェクトの本質に立ち返る良い機会となりました。
今後の予定
叡啓大学では、産学官連携を推進するため、今後も様々なイベントを予定しています。開催日程などの詳細は、公式サイトのカレンダーで確認できます。興味のある方は、ぜひ参加してみてください。実践教育プラットフォーム協議会を通じても、様々なイベント情報が案内されるので、新しい学びの場をお見逃しなく!
公式サイトはこちら:叡啓大学
新たな知識を得て、プロジェクトを推進する力を養うこのようなイベントは、地域の活性化にもつながるでしょう。参加を通じて、自身のスキルも磨ける貴重な機会です。



トピックス(その他)


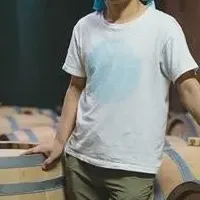


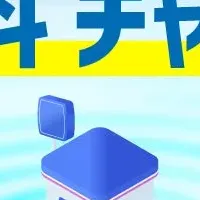




【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。