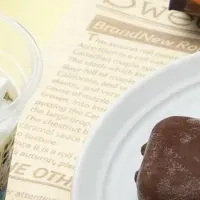
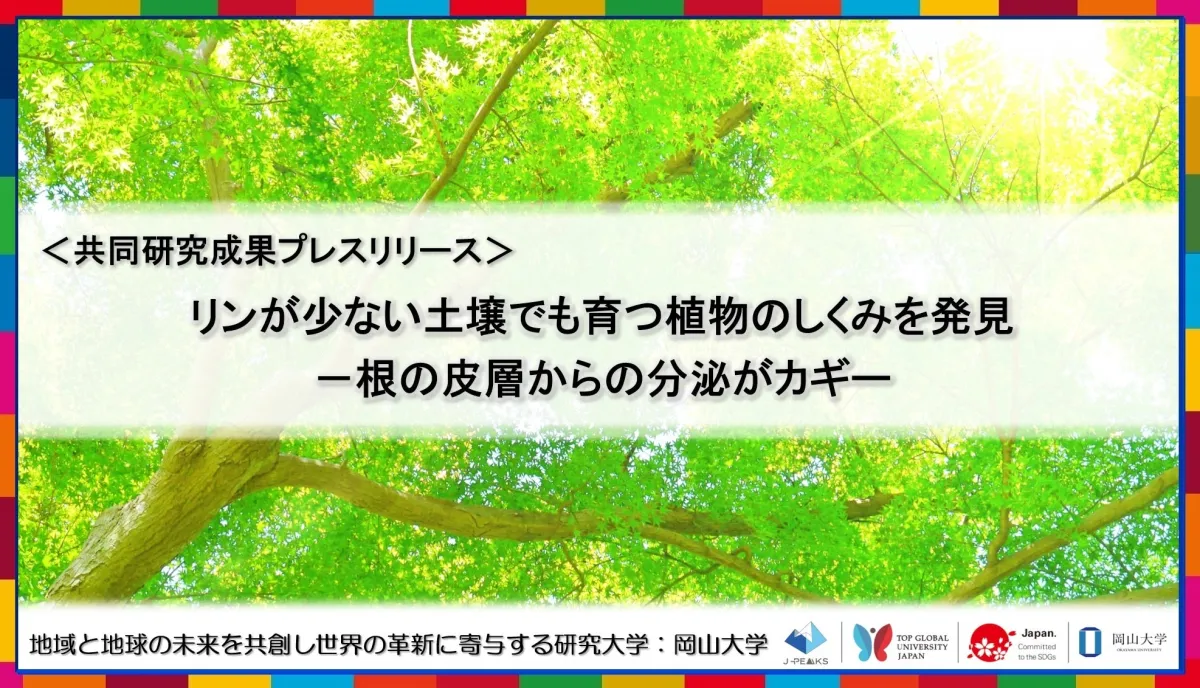
広島大学らが発見したリン不足土壌でも育つ植物の秘密とは?
広島大学らが発見したリン不足土壌でも育つ植物の秘密とは?
広島大学や岡山大学、北海道大学、山形大学の研究チームが、リンが不足した土壌でも育つ植物の仕組みを発見しました。その植物が特に注目されているのは、「超低リン耐性植物」というグループに属するもので、具体的には南西オーストラリアに自生するピンクッションハケア(Hakea laurina)が例として挙げられます。
この植物は、リンが著しく少ない環境においても、特殊な根の形態である「クラスター根」を形成します。クラスター根は、通常の根に比べて側根が密集しており、根の表面積を大きくすることで、効率的にリンを吸収する役割を果たします。さらに、根からは多くの有機酸や酸性ホスファターゼ(酵素)が分泌され、土壌中のリンを吸収しやすい形に変化させるといった特性も持っています。
研究の背景
これまで、植物の根から分泌される物質は主に表皮から出ると考えられていました。しかし、ヤマモガシ科の植物では、分泌に関与する遺伝子や具体的な分泌位置が明らかにされていなかったため、研究の進展が難しい状況にありました。実は、ヤマモガシ科の植物は木本植物で生育が遅く、分子生物学的手法の適用も限られていたため、研究は高い難易度で行われていたのです。
本研究では、特にピンクッションハケアのクラスター根におけるリン受容に関与する遺伝子「HalALMT1」が発見されました。この遺伝子は、根の皮層から分泌物を放出する能力を高める役割を果たします。特に、酸性ホスファターゼの活性染色試験を用いることで、根の皮層組織から有機酸や酸性ホスファターゼが分泌されていることを確認しました。このように、分泌物が根の周辺土壌に効率よく拡散されることが、リン吸収能力の向上に寄与していることが実証されました。
研究の成果と可能性
発表された研究結果は、土壌からの物質侵入を防ぐ「スベリン外皮」が形成されないことが確認され、根からの分泌物がスムーズに周囲の土壌に拡散されることが根分泌能の向上に影響していることが明らかになりました。この成果は、超低リン耐性植物の特性を利用して作物に応用できる可能性を秘めており、農業や環境保全においても非常に重要な意味を持ちます。
論文の概要
今回の研究成果は、2025年6月に発行されるNew Phytologistに掲載予定で、論文のタイトルは「HalALMT1 mediates malate efflux in the cortex of mature cluster rootlets of Hakea laurina, occurring naturally in severely phosphorus-impoverished soil」です。
この研究においては、広島大学からの投稿費用(Article Processing Charge, APC)の助成も受けており、多くの大学の共同研究によって成果が得られました。これにより、今後はリン不足が課題となる地域でも、持続可能な農業が可能になることが期待されます。さらに、この研究が提示する新たな知見は、植物科学の分野での新しい発展の基盤となるでしょう。皆さんも、この学術的な動向に注目してみてください。
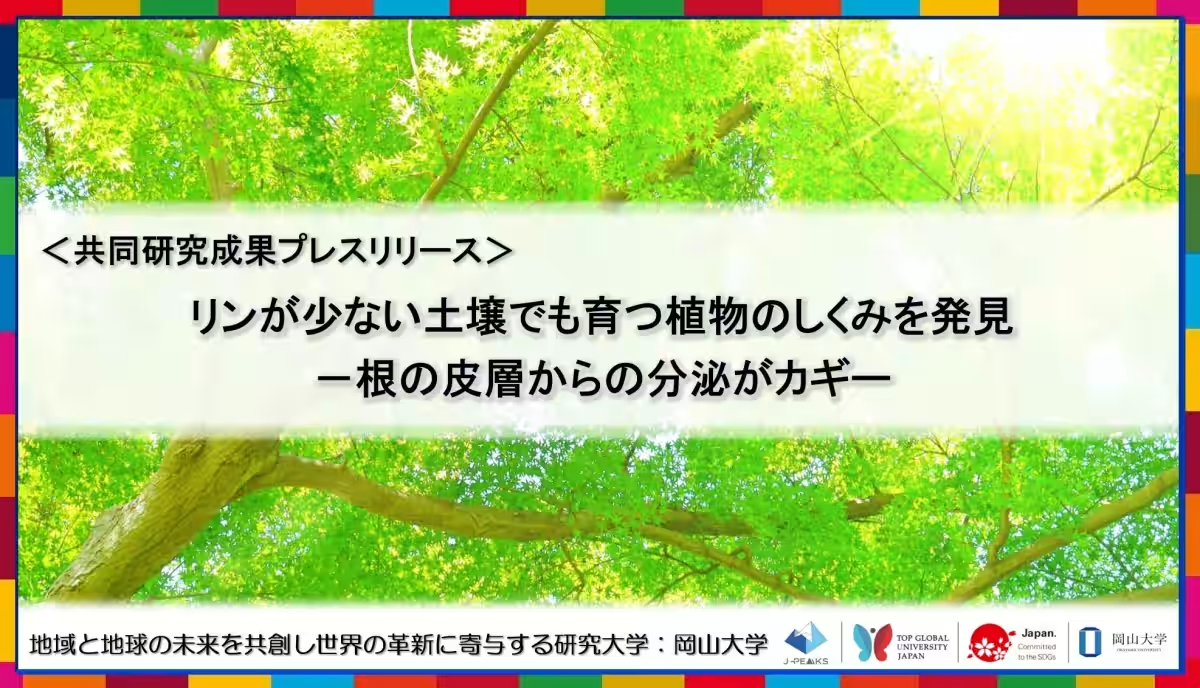



トピックス(その他)
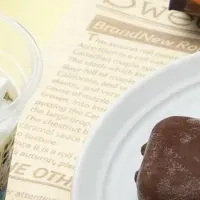
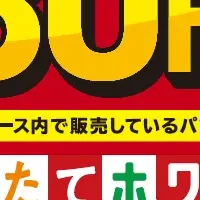





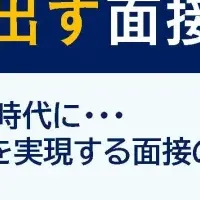

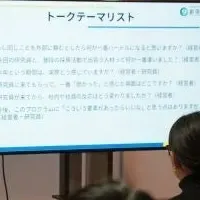
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。