

叡啓大学が実施する共創プロジェクトの成果を報告するイベントについて
叡啓大学が推進する共創プロジェクトの成果報告会
令和7年度上期の共創プロジェクト成果報告会が、2025年9月24日に広島のエディオンピースウィングで開催され、104名の参加者が集まりました。このプロジェクトは、企業、大学、学生が共に課題解決や新規事業の創出を目指す実践型の取り組みです。参加者は会場とオンラインの両方から参加でき、成果発表の様子が広く共有されました。
共創プロジェクトの背景
叡啓大学では、企業が抱える現実的な課題や新しい事業の可能性を追求すべく、学生と企業が手を組む「共創プロジェクト」を推進しています。この取り組みでは、参加学生は有償の雇用契約を結び、実社会で学びを実践する機会を得ます。学生は自由参加であり、大学の授業とは異なる形で新しい学びを経験することができます。
トークセッションの様子
イベントの第一部には、株式会社サンフレッチェ広島の事業本部長、山路瞬氏と、叡啓大学の早田吉伸教授が参加し、トークセッションを行いました。山路氏は新スタジアムの開業に向けた取り組みを説明し、来場者が「来てよかった」と思える空間づくりの重要性について語りました。また、学生との共同作業が企業に新たな視点や発想をもたらすことを強調しました。
成果報告:アクト中食株式会社チーム
第二部では、実際にプロジェクトに取り組んだ2社の成果が発表されました。最初にアクト中食株式会社のチームが発表し、広島の中小農家が直面する後継ぎ問題に焦点を当てました。調査を通じて、担い手不足や後継者の農業理解不足が課題として浮かび上がり、学生たちは「継ぐミライ診断」の提案を行いました。これは、農家の強みや未来の展望を可視化するツールであり、後継者が農業に前向きな関心を持てるような仕組みを目指しています。
成果報告:株式会社シンギチーム
続いて、株式会社シンギのチームが発表しました。彼らは紙コップのリサイクル推進をテーマに、企業と学生が協力して取り組んでいます。リサイクルが進まない背景には、企業のコスト負担があることを指摘し、循環型モデル「Paper Cup Circulation Partnership(PCCP)」を提案しました。このモデルでは、提供から回収、再生までの流れを構築し、地域イベントや商業施設との連携により社会実装を目指しています。
フィードバックと今後の取り組み
各発表の後には、経営者からのコメントや参加者によるフィードバックがあり、活発な意見交換が行われました。叡啓大学では、今後も企業と学生が協力し、新しい価値を生み出すための場を提供していく方針です。興味を持つ企業や団体は、ぜひお問い合わせいただきたいと考えています。
このように、叡啓大学の共創プロジェクトは、地域の課題解決だけでなく、企業や学生の相互成長の機会として位置づけられています。学生の柔軟な発想力と企業の知見が合わさることによって、地域全体に新しい風を吹き込むことでしょう。このプロジェクトは、今後も地域振興や経済発展に寄与し続けることが期待されています。







トピックス(その他)


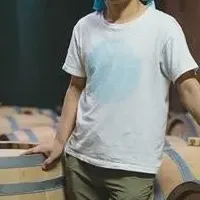


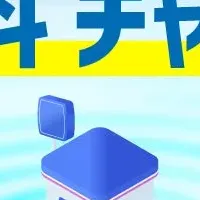




【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。