

叡啓大学の石川副学長が海の未来を考えるフォーラムに登壇
叡啓大学が描く海の未来
2025年9月26日(金)、大阪・関西万博内で開催された「NIKKEIブルーオーシャン・フォーラム」において、叡啓大学の石川雅紀副学長が特別に登壇しました。本フォーラムは、海に関する未来を共に考えることを目的としたもので、多様な分野からの専門家が集い、知見を共有しました。
フォーラムの概要
本フォーラムは、日本経済新聞社と日経BPの主催により行われ、海洋環境や資源循環に関する重要なテーマが取り上げられました。特に、石川副学長が登壇したセッション1「資源循環」では、持続可能な海の利用についての考え方が議論されました。各界の専門家が集まり、それぞれの経験や研究をもとに熱いディスカッションを繰り広げました。
セッション1:資源循環の重要性
石川副学長は、叡啓大学のソーシャルシステムデザイン学部の特徴を活かしながら、社会と環境の持続可能な共生について強調しました。彼はまた、NPO法人ごみじゃぱんの代表理事としても知られ、海洋プラスチック問題に対する解決策の必要性についても言及しました。具体的な政策提言や教育プログラムについてのビジョンを示し、多くの参加者に深い感銘を与えました。
他の登壇者としては、ZERI JAPANの理事長である更家悠介氏、レンゴーの常務執行役員古田拓氏、国連環境計画(UNEP)のプログラムオフィサー本多俊一氏が参加し、それぞれの専門的な視点から意見を交わしました。特に、プラスチックの資源循環や廃棄物管理の観点からの議論が多くの支持を集めました。
参加者たちの反応
フォーラム後、参加者たちは「日常の行動がどのように海に影響を与えているのか考えるきっかけになった」と話し、今回の取り組みの重要性を再認識しました。海洋環境問題は個々の意識改革から始まるという共通の理解が形成され、参加者同士のネットワーキングも活発に行われました。フォーラムでの話を受けて、自発的に地域活動や啓発キャンペーンを立ち上げる動きも見られました。
動画の視聴について
当日の様子は、日経チャンネルNIKKEI CHANNELで視聴可能です。資源循環に関するセッションの詳細や、石川副学長の発言をぜひご覧ください。
叡啓大学では、今後もこのような社会問題に関心を持ち、持続可能な社会を築くための教育と研究を推進してまいります。興味のある方は、ぜひ大学のウェブサイトを訪れてみてください。




関連リンク
サードペディア百科事典: 叡啓大学 石川雅紀 NIKKEIブルーオーシャン
トピックス(その他)


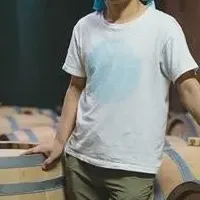


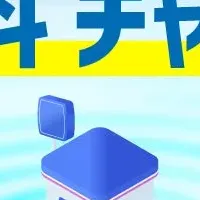




【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。