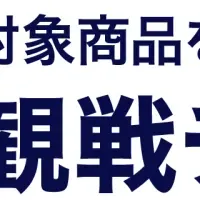

子どもたちが学ぶ海の恵みと持続可能な未来とは?くら寿司の出張授業
くら寿司の出張授業「お寿司で学ぶSDGs」とは
はじめに
2025年11月13日、宍道小学校にて「お寿司で学ぶSDGs」という特別な出張授業が行われます。この授業は、くら寿司株式会社と一般社団法人海と日本プロジェクトinしまねの共同で実施され、児童たちが海の恵みや持続可能な社会について学ぶ貴重な機会となります。
授業の目的と背景
近年、私たちの生活において漁業資源の減少や食品ロスが深刻な問題として取り上げられるようになっています。こうした背景から、子どもたちに「海の恵み」を未来に引き継ぐためには何ができるのかを考えることが重要です。この出張授業では、SDGsの理念を基にした体験学習が行われ、子どもたちに次世代を担う意識を育てていきます。
授業の内容
出張授業は三部構成で行われ、以下のような内容が予定されています。
1. 未来ではお寿司が食べられなくなる!?
児童たちは映像や魚の模型を用いて、海の資源に関する現状を学びます。例えば、日本が直面している資源の減少や気候変動によって変わる魚種について、実際のデータを交えて理解を深めます。
2. お寿司屋さん体験をしよう!
くら寿司が提供するオリジナル教材を使って、児童たちは「お寿司屋さん体験ゲーム」を実施します。選ばれたお客さんの注文に応じて寿司を提供する中で、過剰提供や廃棄の問題に直面し、食品ロス削減の大切さを実感します。
3. 解決案を考えよう!
最後に、グループディスカッションを通じて、どうすれば持続可能な社会が実現できるかを話し合い、発表します。低利用魚の活用やICTを駆使した食品ロス対策といった実際の例を元に、創造的な解決策を見出します。
隠岐諸島での体験学習
授業の一環として、海と日本プロジェクトinしまねが行った「隠岐めしと歴史探険隊」の体験が紹介されます。2025年7月には、隠岐諸島で20名の小学生が参加し、漁業の現状や海産物の歴史を学びました。尸アイカやシロイカの捌き方、郷土料理の調理にもチャレンジしたことで、地元の伝統と現代的な課題を体験的に理解しました。この体験学習の様子を収めた動画も上映され、児童たちが自らの住む地域でもこのような課題が存在することを実感できる構成になっています。
参加校と地域への広がり
この出張授業は、宍道小学校の他にも松江市内の3校で行われる予定です。学校や地域に広がるこの取り組みは、持続可能な社会への理解を深めるための大きなステップになるでしょう。授業の内容を通じて、子どもたちが豊かな海とその恵みを未来に繋げていく意義を感じられることが期待されます。
取材のご案内
授業の内容に関連した商品が、松江市内のくら寿司店舗で取材可能とされています。たとえば、「旬の海鮮丼」や「海鮮ユッケ」、さらには地域の特産を活かしたカニみそなど、地元の海の恵みが詰まった料理を取材することができます。この機会にぜひ、島根の海の現在と未来に関する情報を発信してください。
結論
「お寿司で学ぶSDGs」出張授業は、子どもたちにとって学びを楽しむとともに、未来の地球と海を守る意義を考える貴重な経験になります。この授業がきっかけで、子どもたちが自分たちの役割を認識し、持続可能な社会を共に築いていくことが期待されています。ぜひご注目ください!



関連リンク
サードペディア百科事典: 島根県 海と日本プロジェクト くら寿司
トピックス(イベント)
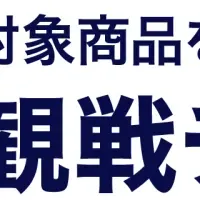
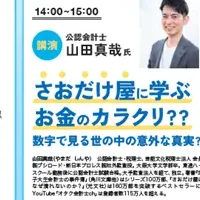




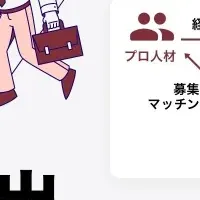



【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。